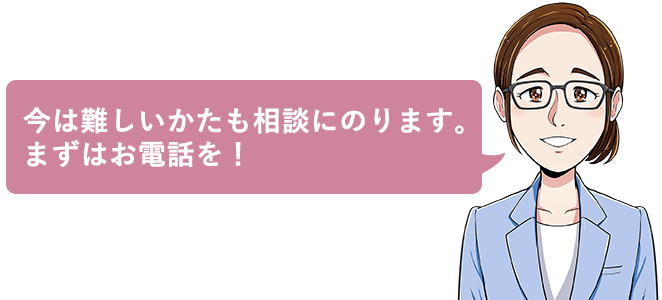- 建設業許可を取りたいけど、何からはじめていいかわからない。
- 役所の手引を読んだけどよくわからない。
- 必要な書類って何?
- 費用はどれくらい必要?
- 許可を取るまで、どれくらいの時間がかかる?
- 許可を取る前に会社を設立したほうがいい?
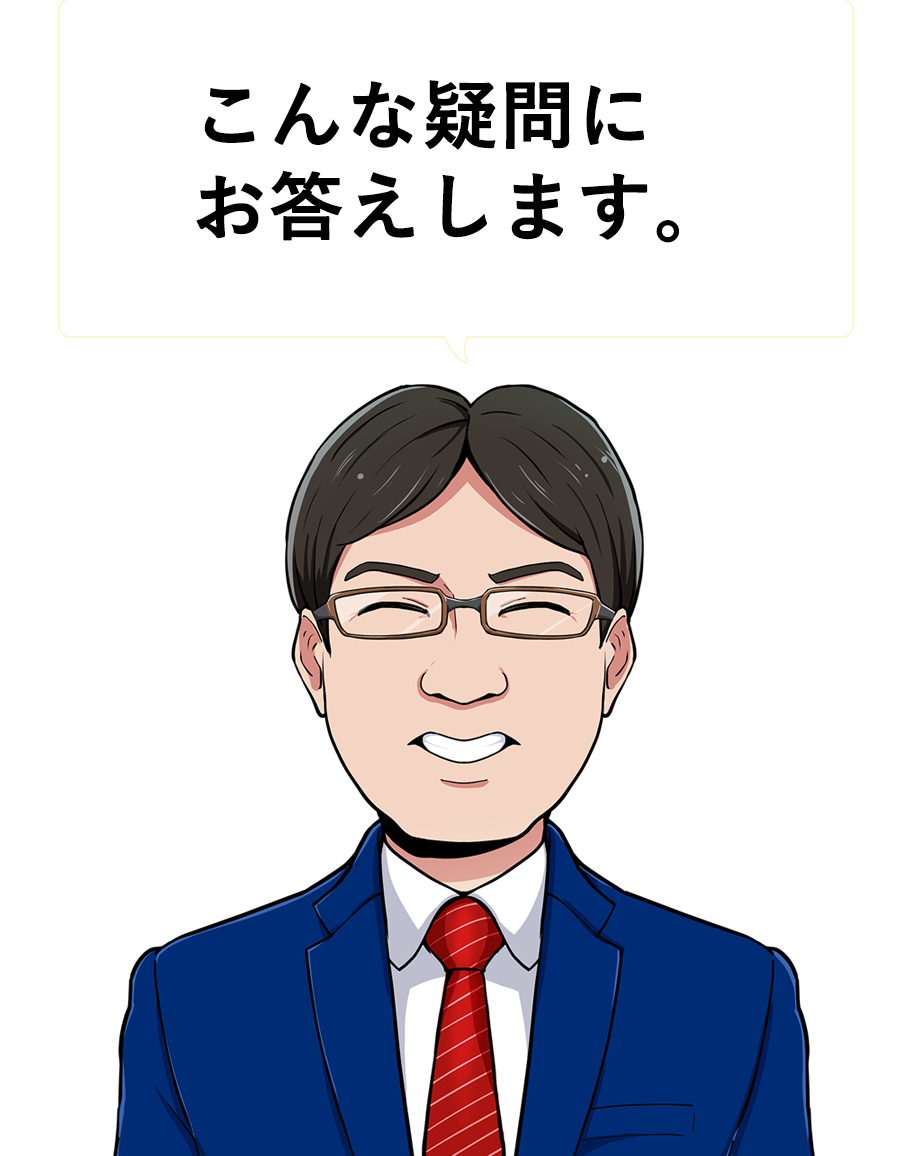
①建設業許可は必要?
建設工事の完成を請け負う場合は、建設業許可を取得しなければ行うことができません。「軽微な工事」以外の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
「軽微な工事」とは・・・
- 建築一式工事以外の場合で500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合で1,500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合で延べ面積が150㎡未満の木造工事
つまり上記の「軽微な工事」だけを請け負う場合には、許可を取得する必要ありません。
②許可取得のメリットは?
1. 信頼度が上がる!
建設業許可は誰でも簡単に取れるわけではありません。
許可を取るということは、「施工技術・資力・経営力・信頼のある業者」といお墨付きを役所からいただけるということです。そのお墨付きがあれば、お客さまからも他の建設会社からも信頼を得られることになります。
また、最近は元請会社のコンプライアンスが厳しくなってきているため、許可を取得している業者でないと工事を発注してもらえないという話もよく聞きます。
2. 大きな契約ができる!
許可を取ると500万円以上の工事を請けられるようになります。許可の取得には最低でも1ヶ月はかかりますので、今のうちから許可を取得の準備をしておけば、急に大きな工事を請け負うことになっても安心です。
3. 公共工事に入札できる!
公共工事の入札の流れは、建設業許可を取得→経営事項審査→入札参加資格申請となります。まずは、建設業許可の取得が必要です。公共工事を落札することにより売上アップにもつながります。
③建設業許可について
許可の種類って?どれに該当するか?
建設業許可の種類は以下の29種類になります。(以前は28種類でしたが、平成28年6月から「解体工事」が追加され29種類となりました。)
- 1.土木一式工事
- 2.建築一式工事
- 3.大工工事
- 4.左官工事
- 5.とび・土工・コンクリート工事
- 6.石工事
- 7.屋根工事
- 8.電気工事
- 9.管工事
- 10.タイル・レンガ・ブロック工事
- 11.鋼構造物工事
- 12.鉄筋工事
- 13.舗装工事
- 14.しゅんせつ工事
- 15.板金工事
- 16.ガラス工事
- 17.塗装工事
- 18.防水工事
- 19.内装仕上工事
- 20.機械器具設置工事
- 21.熱絶縁工事
- 22.電気通信工事
- 23.造園工事
- 24.さく井工事
- 25.建具工事
- 26.水道施設工事
- 27.消防施設工事
- 28.清掃施設工事
- 29.解体工事
29種類の中には、2つの一式工事と27の専門工事があります。
一式工事とは、土木工事や建築工事を総合的に企画、指導、調整して行う工事なります。
その他の工事は専門ごとに27にわかれています。
どの許可で取ればいいのかは、実際行っている工事の内容によって取得する業種を決めます。大工工事を行っているなら、「大工工事」、塗装工事を行っているなら「塗装工事」となります。
よく勘違いされるのは、一式工事の許可を取れば全部の工事ができると思われる方がいますが、一式工事で全部の工事ができるわけではありません。一式工事はあくまでも自らが元請業者となって、工事を総合的にマネジメントする立場の時です。専門工事を行う場合はそれぞれの専門工事の許可を取る必要があります。
また、要件を満たせば、複数の許可を同時に取ることできます。許可を取ったあとに、申請すれば業種を増やすこともできますが、手数料が5万円かかりますので、最初の時点でまとめて取っておくほうがお得です。
当事務所でお客さまの工事の内容をしっかりとお聞きしてどの許可を取ればいいのかアドバイスをいたします。
一般か特定かどちら?
建設業許可取得の際には「一般」の許可か「特定」の許可を選択することになります。
その違いはなんなのかというと、「特定」の許可は自分が元請業者になるかどうか、ある一定以上の金額を下請に出すかどうかになります。
「特定」の許可が必要な場合は・・・
発注者から直接請負う工事について4000万円以上を下請に出す場合
発注者から直接請負う建築一式の工事について6000万円以上を下請けに出す場合
以上の場合以外は「一般」の許可になります。ややこしい話になりますが、一次下請業者から二次下請業者に下請を出す場合は、上記の金額を上回っていても「一般」の許可で大丈夫です。また、自らが元請業者として1億円の工事を請け負ったとしても、すべての工事を自社で行う場合や、上記の金額より低い額を下請けに出す場合は「一般」の許可で大丈夫ということになります。
大臣許可?知事許可?
実際に建設業を行う営業所がいくつあるかで許可の申請先が変わってきます。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 → 大臣許可
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合 → 当道府県知事
「営業所」とは工事の契約を締結する事務所のことをいいます。実際に建設業を行わない店舗は「営業所」にはあたらないことになります。
なお、大阪府知事で許可を取っても、全国どこでも工事をすることはできます。
大阪で許可を取り、新たに東京に営業所を出したいという場合は、大阪府知事許可から大臣許可に申請をし直すということになります。これを「許可換え新規」といいます。
許可の期限は?
建設業の許可の期限は5年になります。そのため、5年ごとに更新をしなければ、許可はなくなってしまいます。
また、1年に1回決算変更届の提出も必要になります。
許可申請にかかる実費は?
建設業許可を取得するためには、申請手数料が必要です。
新規許可の場合
知事許可・・・9万円(証紙代)
大臣許可・・・15万円(登録免許税)
更新許可の場合
知事許可・・・5万円 大臣許可・・・5万円
その他に、登記されていないことの証明書、身分証明書等を取るための費用が必要になります。

どういう許可になるか診断してみましょう!
お客様がどの許可申請に該当するのか確認してみましょう。
①営業所の数
Q. 営業所は何ヶ所ありますか?
- 1ヶ所だけ
- 同じ都道府県に
2か所以上 - 異なる都道府県に
2か所以上
②工事の請負方について
Q. 工事は発注者から直接請ける(元請)ことが多いですか?
下請で請けることが多いですか?
- 元請が多い
- 下請が多い
③許可の取得について
Q. 会社として許可を取りたいですか?
個人で許可を取りたいですか?
- 会社
- 個人
あなたの場合は・・・

- 戻る
④建設業許可の要件
まずは建設業許可が取得可能か簡単チェック!
実際に許可が取れるか確認していきましょう。許可を取るためには5大要件をクリアする必要があります!
下記の質問にYES または NOで回答してください。
①経営業務の管理責任者
Q. 許可を取ろうとする業種の経営経験は5年以上ありますか?
- YES
- NO
②専任技術者
Q. 許可を取得する業種の資格か、実務経験が10年ありますか?
- YES
- NO
③財産要件
Q. 500万円の預貯金がありますか?
- YES
- NO
④使用権限のある事務所の有無
Q. 許可を取る事務所はありますか?
その事務所は自分所有ですか? 賃貸ですか?
- YES
- NO
⑤誠実性・欠格要件
Q. 5年以内に反社会的勢力に属していませんか?
- YES
- NO
あなたの場合は・・・
許可が取得できます!

- 戻る
5大要件の詳細について確認しよう!
実際に許可が取れるか確認していきましょう。許可を取るためには5大要件をクリアする必要があります!
これらの要件は全て満たしている必要があります。しかし許可を満たしているかどうかの判断には時間が掛かるケースもあります。当事務所にご相談頂ければ、スピーディーに要件該当性を判断いたします。また、万が一許可が取れないという判断に至った場合も、要件を満たすための具体的なアドバイスをいたします。
経営業務の管理責任者とは?
建設業の許可を取るためには、事業所に必ず1人は「経営業務の管理責任者」を置かなくてはなりません。
「経営業務の管理責任者」とは、簡単に言うとつまり、経営できる能力がある人ということです。
建設業の経営は普通の事業と違って特殊なもの。誰でも簡単に経営できるわけではありません。なので、経営できる能力がある人をいうのが求められます。それはどんな人かと言うと、過去に建設業を一定以上経営していたという経験がある人ということになります。
例えば、法人であれば取締役、個人事業であればその事業主といった、一定以上の地位においての経営経験が必要です。経営経験も1年あればいいといわけではなく、一定以上の年数が必要です。
経験年数は何年必要かというと
許可を受けようとする業種に関しては5年
許可を受けようとする業種以外に関しては6年
取締役でも個人事業主でもなかったけど、どうしたらいいの?という方、安心してください。「準ずる地位」というものがあります。どいうった形で働いていたのかをしっかりとヒアリングしてアドバイスをいたします!
専任技術者とは?
「専任技術者」とは、つまり、工事をする技術を持っている人がいるかということです。
建設業許可を取るためには、営業所ごとに「専任技術者」をおかなくてはいけません。「専任」というくらいなので、常時営業所に勤務していなければなりません。他の会社と兼任することはできません。
「専任技術者」になるためには、資格を持っているか、10年以上の実務経験が必要です。10年の実務経験は口で言うだけではダメです。工事の請求書や確定申告書といった書類で証明が必要です。必要な書類が揃わなければ専任技術者になることはできないので注意が必要です。
他にも以下の場合は専任技術者になることはできません。
他の営業所の専任技術者になっているとき
他の建設業者の専任技術者となっているとき
他の建設業者の経営業務管理責任者となっているとき
他の建設業者の国家資格者として登録されているとき
住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能と判断されるとき
「財産的基礎」とは?
建設業許可を取るためには、資金力や金銭的信用も必要となります。建設業の工事は大きな金額の工事になることがあります。工事の途中で会社が倒産ということになったら大変ですから、お客様を保護するためにも金銭的な信用がとても重要になります。
特定許可の場合は、一般許可と違い財産的要件がとても厳しくなります。
財産的基礎の要件
一般許可の場合
以下のどれかに該当することが必要です
直前の決算において、自己資本の額が500万円以上(法人の場合、決貸借対照表の株主資本の額になります)
500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の発行する500万円以上の残高証明書)
建設業許可を受けて5年間営業した実績があること
特定許可の場合
以下の4つすべてに該当することが必要です
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・法人の場合
{繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+任意積立金)}÷資本金の額×100≦20%
・個人の場合
{事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)}÷資本金の額×100≦20%
流動比率が75%以上であること
流動資産÷流動負債×100≦75%
資本金の額が2000万円以上であること
・法人の場合
株式会社の場合・・・払込資本金
持分会社の場合・・・出資金額
・個人の場合
期首資本金
自己資本の額が4000万円以上であること
・法人の場合
貸借対照表の純資産の額≧4000万円
・個人の場合
貸借対照表の(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4000万円
「誠実性と欠格要件」とは?
建設業でいう「誠実性」とは、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないということです。
「不正な行為」とは、「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」です。
「不誠実な行為」とは、「工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為」です。
建設業の主な欠格要件は以下のとおりです。1つでも欠格要件に該当していたら許可は取れません。欠格要件の対象となる人は、法人でいえば、取締役、執行役員、100分の5以上の株を持っている株主、相談役顧問等、会社に対して支配力を持っている人、個人でいえば、個人事業主です。
主な欠格要件は
成年後見人、被保佐人
破産者で復権を得ない者
建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予の場合は、執行猶予期間中は欠格要件に該当する)
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員等がその事業活動を支配する者
営業所とは?
建設業の営業所とは、請負契約を締結、請負契約の見積り、入札など実体的な行為をする場所になります。
単なる連絡事務所だったり、登記上だけの本店・支店や建設業をしない本店・支店は営業所にはなりません。
建物が自己所有なのか、賃貸なのかで必要な書類が変わってきます。賃貸の場合、賃貸契約書の使用目的が「居住用」になっていると営業所として使えないので要注意です。